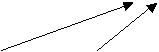 |
|||
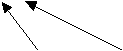 |
高齢者の「居場所」に関する心理学的研究
相田 めぐみ
本研究では、後期高齢者も含めた高齢期の精神的な充足の問題について考えるため、「居場所」という言葉に注目した。
「居場所」についての先行研究は、青少年についてのものが多く、また、「居場所」に関しては確立された心理学的尺度や共通して使用されている定義はみられなかったため、高齢者へのインタビュー調査を予備調査とし、新たな居場所モデルの提案を試みた。
本研究における仮説は、「居場所感は、物理的居場所、社会関係的居場所(所属感、家族、友人)、役割的居場所(虚脱感、無力感)、自己内目的的居場所の4つのサブカテゴリーからなる。(図1)」という居場所モデルであった。ここでの各サブカテゴリーの定義は次のとおりである。
【居場所感のそれぞれのサブカテゴリーの定義】
・
物理的居場所とは、居場所を感じられる物理的場所があるかないかである。
・ 社会関係的居場所は、主に、「関係」(―人間関係、組織との関係)にかかわるものである。社会関係的居場所には「家族」「友人」「所属集団(セカンダリーグループ)」にかかわるものがあり、それぞれの果たしている機能である。「所属集団」は会社組織などセカンダリーグループへの帰属意識、所属感を表す。「家族」「友人」はそれぞれとの親密な関係を表す。
・
役割的居場所とは、「社会の中で」役割があるか(社会にとっての存在価値)、にかかわるものである。「役割的居場所のなさ」には、できるのに役に立てない、という「虚脱感」と、役に立つこと自体ができない、という「無力感」がある。
・
自己内目的的居場所は、あくまで「自分のための」やること、楽しみ、にかかわるものである。
包括的居場所感
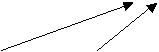
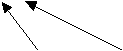
物理的 社会関係的 役割的 自己内目的的
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
所属集団 家族 友人 虚脱感 無力感
本調査は東京都大田区の60歳以上の男女を被調査者とした郵送調査であった。郵送調査の回収率は59.6%(470/788)であった。
結果、仮説における居場所モデル(居場所感は物理的居場所、社会関係的居場所(所属感・友人・家族)、役割的居場所(虚脱感・無力感)、自己内目的的居場所の4つのサブカテゴリーからなる)より、「物理的居場所、所属―友人、家族的居場所、役割的居場所(虚脱感・無力感)、自己内目的的居場所」の5つのサブカテゴリーからなる居場所モデルの方が、数値上、よりふさわしいのではないかと考えられたが、仮説における居場所モデルも割合よいモデルといえそうであった。
この、新しい居場所モデルでは、「居場所サブカテゴリー全てが高いというわけではなくても、包括的居場所感は高い、という状態もある」、と想定されており、分析の結果、年齢や性別のデモグラフィックグループ(男/女・前期高齢者/後期高齢者)によって、それぞれのサブカテゴリーの重要性が異なり、それぞれのサブカテゴリーの包括的居場所感に対する効果が異なる、ということが見られた。
また、いくつかのサブカテゴリー間に補填作用(ある一つのサブカテゴリーが低い人でも、別のサブカテゴリーが高いことによって、包括的居場所感が低くなるのが阻止されること)がみられた(男性の家族的居場所の所属感に対する補填作用、前期高齢者の家族的居場所の役割的居場所に対する補填作用)。
本研究では、家族的居場所、役割的居場所、自己内目的的居場所の規定要因についても分析を行ったが、その中にはデモグラフィックグループごとに違う効果の見られる規定要因もあった。この点については、今後、より発展的な研究が望まれる。また、家族的居場所、役割的居場所、自己内目的的居場所以外の居場所サブカテゴリーの規定要因については、今回の研究では検討されていないため、今後の課題として残された。